万延元年(1860年)3月3日。現在の暦では4月中旬に当たる季節外れの大雪の日、60名近い一行に守られた大老・井伊直弼が、たった18名の暗殺者によってあっけなく首級を奪われた。この桜田門外の変によって幕府の権威は地に落ちた。
その1ヶ月前、八郎は
「虎尾の会」を結成した。国を守るためならば虎の尾を踏む危険も恐れない、という意味である。ここに集まったのは直参旗本の山岡鉄太郎(鉄舟)、松岡万、薩摩藩士の伊牟田尚平、益満休之助をはじめ15名。
目的は
尊皇攘夷-外国人を日本から追い払い、天皇を中心に日本をひとつにまとめて事に当たる-というものだ。

アメリカのペリーが黒船4隻を引き連れてやってきたのが嘉永6年(1853年)、井伊直弼大老が天皇の勅許(許可)を得ずに日米通商条約に調印したのが安政5年(1858年)。以来、外国との貿易が始まるや日本国内はさまざまな混乱をきたすようになった。民衆に真っ先に押し寄せてきたのは物価の急上昇だ。米をはじめ日常品の値段が鰻登りに上がった。それに、いずれアメリカ、イギリスは日本を清国のように武力で征服し、植民地にしようとしている・・・それなのに、幕府はアメリカの脅しに負け、いいなりになっている。そんな矢先に、大老暗殺という前代未聞の大事件が起こったのだから、幕府は面目丸つぶれ、民衆は赤穂浪士の討ち入りをした47士をたたえるように大老の首を取った18士をたたえた。
「天下の形勢、内潰の外これ無く候」
ほうっておいても幕府は内部からつぶれてしまうだろう。だが、幕府が自然消滅するまで待っているわけにはいかない。幕府の崩壊に日本国民が道連れにされたのではたまったものではない、と八郎は考えた。八郎が学んだ学問は「経世済民」、つまり国を治め民を救うのが目的である。すでに学者としては一流である。これからは自分が学んだ学問を実践に移す時なのだ。
「丈夫書を読む豈天下を経理せざるべけんや」
学問を積んだ立派な人物が世の中をよい方向に導くべきである。つまり机上を離れ、行動を移してこそ学問に意義があるのだ、と八郎は言っている。
同じ年の12月5日、アメリカ公使館通訳のヒュースケンが暗殺された。実行者は伊牟田尚平ら虎尾の会同志だった。これによって清河塾への幕府の監視の眼が光り、危機はひしひしと八郎に迫ってきた。
翌年の文久元年(1861年)5月20日、八郎にとって運命的な事件が起こった。水戸の志士に呼ばれて両国へ行った帰り道、八郎は6尺棒を持った妙な男に道ばたでからまれた。あきらかにケンカを売っている。
「無礼者!」
|
八郎の白刃は抜き打ちざま男の首すじをとらえ、一閃した。胴を離れた頭は2メートルばかり飛んで、瀬戸物屋のどんぶりにゴロンと入った。
ともに歩いていた山岡鉄太郎さえ気づかなかったくらいの早業だった。が、これが捕り手の罠だった。誤算はまさか八郎がこれほどの使い手だとは思ってもいなかったことだ。
頭を無くした男が血を吹き出してどっと倒れるや、待機していた捕り手方がいっせいに押し寄せてきた。
|
 |
だが、皆ぶるぶる震えて、腰が引けている。そのすきに八郎たちは夜の闇に紛れて逃げていった。こうして八郎は幕府のおたずね者となって1年半におよぶ逃亡生活が始まった。
虎尾の会同志はばらばらになった。
八郎の妻・お蓮、弟・斎藤熊三郎、池田徳太郎、石坂周造、北有馬太郎など計8名が牢獄に入れられた。このうち、生きて出てこれたのは3名だけだった。
また、故郷の清川村でも父母が拷問され、さまざまに名目を立てては金品を強要され、何百両という大金が奪われていった。
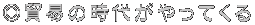
八郎は安積とともに逃れ、仙台に潜居していた時、偶然にも同じく逃れてきた同志・伊牟田尚平とはちあわせとなりった。
 |
そして伊牟田に、
「水戸藩士が決起して、天皇を奉じて天下に号令するために上洛する動きがある。自分は故郷・薩摩に戻って同志を集い、その動きに応援したい。」
という情報を聞かされる。八郎はこれを良策とはせず、幕府側の廃帝の動きを察し、これを止めるために上洛し、田中河内介(朝廷・中山忠能の侍読)に頼り密かに天皇に封事を賜り、薩摩藩の同志を募り勤皇の詔を奉じて挙兵する策を押したのだった。八郎の志は固まった。
八郎はマイナスをプラスに転じようと考えた。幕府のおたずね者になったのだから、これからは堂々と尊皇攘夷の志士として活動しようと。
八郎は精力的に全国を遊説して回った。
|
「関東方面は外国人が入り込んで、幕府役人たちの卑屈な態度と外国人たちの悪逆ぶりを皆知っているので<攘夷>を訴えたほうがいい。一方、関西方面は外国人の脅威をまだ知らず、幕府の弱腰のみが聞こえているので<尊皇>を合い言葉にしたほうがわかりやすい」
民衆の生活実感を考えて、八郎は「関東は攘夷、関西は尊皇」と見抜いていたのである。
文久元年(1861年)10月、八郎は安積五郎、伊牟田尚平とともに上洛し、中山忠能の長子・忠愛から志士に送る書簡を預かり、九州遊説についた。さらに八郎は西国に遊説し、真木和泉、村松大成、川上彦斎などとも会談し方策を練った。
- ところで、清河八郎は現在、過激な「攘夷論者」と考えられているようだが、本当にそれだけだったのだろうか?「神国日本に夷狄(野蛮な外国人)を入れてはならない」という、時代の流れに逆らう頑迷固陋なだけの人物だったのだろうか?ところが、このような話が伝えられている。のちに生糸などの貿易で巨利を得て<天下の糸平>といわれ、大実業家となった田中平八が、旅先で清河八郎に会い、八郎から
「これからは貿易の時代がやってくる。生糸をあつかったら成功するよ」
といわれたという。これはどういうことなのだろう?
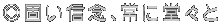
清河八郎は21歳の時、九州を旅し、長崎の出島にオランダ商館を見学した。外国を知るためにオランダ語を勉強しようとしたこともあった。23歳の時、黒船を見に浦賀へ出かけている。24歳の時、ロシアへの脅威にどのように備えているかを視察するため、蝦夷(北海道)にまで足を伸ばしている。八郎は常に、「時代」を客観的見ようとしていたのだ。さらに特記すべきことは、幕府がペリーと日米和親条約を結んだ安政元年(1854年)、八郎が25歳の時のことである。
土佐藩の間崎哲馬に宛てた手紙に次のようなことを記している。
「ロシアがしばしば貿易を願うのに、幕府は国法にふれると言って拒んできた。それなのにアメリカには許した。遠いアメリカに厚く接し、近隣のロシアに冷たくするのは誤りである。」
アメリカは初めから武力にものを言わせる外交で日本を脅しつけてきた。一方、ロシアは非常に紳士的な態度で、日本の立場を尊重して外交に当たった。結局、「野蛮な東洋人」と馬鹿にしきったペリーのほうが成功したのである。それに屈服した幕府が、八郎は何よりもゆるせなかった。隣の清国の二の舞をしたら日本は滅びる。常に堂々と、対等な立場でなければならない、というのが八郎の信念だったのである。そのためには、外国人に一泡吹かしてやらなければならない。それが八郎の攘夷であり、腰抜け外交の幕府を滅ぼすのが八郎の尊皇だったのである。「清河八郎」(昭和49年、新人物往来社刊)の著者、小山勝一郎氏は
「八郎の攘夷は、ある条件さえそろえば、開港に変ずる」と記している。
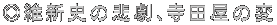
京都へ、九州へ、八郎は歩きに歩いた。1日に15里(60km)はざらだ。一時間に約1里(4km)歩くとして、15里だと15時間も歩きづめである。全国の志士に檄を飛ばし歩き続け、ついに「京都挙兵」が現実のものとして動き始めた。
文久2年(1862年)4月、薩摩藩の島津久光が一千の兵を引き連れて京都に上る。これを機に天皇の旗印(錦旗)のもと、一気に攘夷倒幕を決行しようというものである。
この計画の中心に、朝廷に詳しい田中河内介と行動家・清河八郎がいた。八郎の呼びかけに薩摩藩士をはじめ全国の志士が続々と京都に集まってきた。志士たちは「京都挙兵」の成功を疑わず、ついに自分たちの時代が来たのだと喜んだ。
が、一人だけさめていた人物がいた。清河八郎である。朝廷を動かし攘夷ののろしをあげるのは可能だが、薩摩の久光公を動かすことはできない、と八郎は見抜いていたのだ。しかし、薩摩藩の急進派は成功を急ぎ、その判断ができなかった。久光公の考えは、「公武合体」にあったのである。
幕末維新史に残る悲劇がやってきた。
文久2年4月23日、京都・伏見の寺田屋で起こった悲劇
「寺田屋の変」である。
久光公に挙兵の考えは無く、挙兵の動きを察知した久光公は、「挙兵」を信じていた過激志士の粛清を命じたのだった。同じ薩摩藩士同士の斬り合いとなり、多くの有能な志士が無念の死を遂げたのだった。
後日、薩摩藩邸に留まっていた、他藩の田中河内介ら挙兵を試みた志士たちも惨殺された。
八郎は田中と意見が合わず、薩摩藩邸を出ていたため、運良くその一命を失わずにすんだのだった。

