藤本鉄石との運命的出会いは、元司(八郎)の江戸遊学の志を確実なものとした。
弘化4年(1847年)5月2日、まだ明けやらない早朝、18歳の八郎は枕元に遺書を残して清川村を出奔した。
再三再四、祖父・昌義と父・豪寿に江戸へ勉強に行きたいと言ったが、どうしても許してもらえなかった。元司(八郎)は斎藤家のあととりであり、いったん江戸に行かせれば元司(八郎)の気質からして家業を継ぐ気持ちが失せてしまうことは一目瞭然であり、それを考えれば認めることは出来なかった。
ところが、元司(八郎)の学問の先生であった清川関所役人・畑田安右衛門が江戸へ転勤と決まった。チャンス到来である。
「私も江戸に連れて行ってください!」
と八郎は畑田に頼んだ。
元司(八郎)の才能を惜しんだ畑田は、親に背いて家出する元司(八郎)に協力することにしたのである。畑田先生との待ち合わせ場所は上山の温泉宿であった。ところがいくら待っても畑田先生はやってこない。どのくらいの時間がたったのだろうか、ふと見ると、斎藤家の使用人が一軒一軒旅籠(旅館)を覗いている。使用人に声をかけると、急遽江戸行きが中止になり畑田先生はこれないと言う。八郎は愕然とし不安になったが、今さら志を曲げるわけにはゆかず、ましてや戻ればもう二度とチャンスは無いかもしれない。このままあきらめるわけにはゆかない。
元司(八郎)は単身で江戸へ向かった。
清川を出て16日目、江戸に到着した。
元司(八郎)は、
「この日、初めて富岳(富士山)を見る」と日記に記した。富士の霊峰は、日本の中央についに来たという深い感動を元司(八郎)に与えたことだろう。八郎の胸は高鳴った。
東条一堂塾に入った元司(八郎)の勉強ぶりはすさまじかった。22歳の日記に、
「まだまだ努力が足りない。これからは午前2時まで勉強し、机で2時間くらい居眠りをし、それからまた勉強して決して寝床には入るまい」
と誓ったとある。こうした日課を元司(八郎)は実際に74日間も続けたものである。
東条塾に入ってほんの1ヶ月で元司(八郎)の勉強ぶりには驚異の眼で見られるようになった。まさに水を得た魚のように生き生きとはげみ、のちに東条一堂門3傑の1人に数えられるほどになった。嘉永4年(1851年)には東条塾の塾頭に推挙されるが、昌平坂学問所を志し当時最高学府の安積良斎塾に移る。
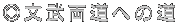
嘉永3年(1850年)、21歳。八郎が京都、九州へと旅をしたとき、数人の追いはぎに囲まれた。そこへ中津藩の武士が通りかかり、助けられた。
「文事ある者は必ず武備あり」-学問のある者は武術にも優れているべきである、という孔子の言葉を、このとき八郎はいやというほど思い知らされたのだった。17歳の時、武芸にも優れていた藤本鉄石の影響もあり、酒田の伊藤弥藤治に剣を習っているが、江戸遊学を目指し、ひたすら学問に没頭していた元司(八郎)にとって、その素質はあっても、そのときは剣にそれ程の関心は無かった。
「大志を持つものなら剣も極めなければなるまい」
嘉永4年(1851年)、22歳の2月1日から、元司(八郎)は神田お玉が池の北辰一刀流千葉周作道場「玄武館」に通い始めた。いったん武術を始めると、八郎の修練ぶりは並大抵のものではなかった。学問と同じく、元司(八郎)は初志貫徹タイプの人間で、一度志したものには妥協を許さず徹底していた。
当時、北辰一刀流・千葉周作の玄武館、神道無念流・斎藤弥九郎の練兵館、鏡新明智流・桃井春蔵の士学館を江戸の三大道場といっていた。
田舎修行3年は江戸修行1年に当たり、なかでも玄武館は名門中の名門だ。普通、道場には5日に1日、月に6日通うのだが、元司(八郎)は違った。毎月20日から25日くらい通っている。平日の2倍は稽古をする寒稽古ともなると、1日も欠かさず出席した。
元司(八郎)はめきめき腕を上げた。
普通、「初目録」をもらうのに2,3年かかるところ、八郎はわずか1年でもらっている。その上が「中目録免許」、さらに上が「大目録皆伝」となる。中目録免許をもらうと師範になれ、自分の剣道場を開ける。八郎が中目録免許を得たのは29歳の時、そして万延元年(1860年)、31歳にして北辰一刀流兵法免許を得た。
ちなみに坂本龍馬も同門で、八郎と龍馬の試合の記録がある。
八郎が『北辰一刀流中目録免許』を受けた安政5年(1858年)、八郎29歳、竜馬24歳の時のことで、竜馬は『北辰一刀流長刀兵法目録』一巻を伝授されている。
龍馬は千葉周作の弟・定吉道場で修練しており、親善なのか稽古なのかは定かではないが、結果は、八郎の圧勝。年齢と経験の差はあるものの、一片の隙も無い八郎に圧され、龍馬は八郎から1本も取ることが出来なかったという。
龍馬は、この時の八郎の姿を、『巨岩』『巨虎』と比喩し敬意を払っている。龍馬は八郎の剣威を絶賛し、八郎もまた、その屈託のない竜馬の人柄に敬意を表し、倒れた龍馬に手を差し伸べたと言う。
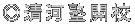
江戸の湯島聖堂に天下の秀才が集まる「昌兵黌」があった。東京大学の前身で、当時の最高学府である。ここに入るため、元司(八郎)は安積艮斎塾から推薦を受け、安政元年(1854年)3月、25歳の時、晴れて昌兵黌に入学した。
が、入ってみるとこれほどつまらないところもない。確かに皆秀才ぞろいだが、実際の学問より「○○大学卒」といった箔をつけるのが目的のような、いわば権威主義の固まりである。
八郎は故郷に手紙を書いた。
 |
「学問のためにはまるでなりません。昔から聖堂のより大豪傑が出たことはありません。田舎では公儀の聖堂といえば大変なものと思っているでしょうけれど、実際はとるに足りないところです。」
八郎は昌兵黌をやめ、神田三河町に開塾した。文武両道を冠した「清河塾」である。25歳という若さだから、江戸で最年少の学者誕生である。このとき初めて、斎藤元司改め「清河八郎」と名乗った。故郷・清川の川の字を大河の河に変えたのである。 |
「経学・文章指南 清河八郎」と看板を出すと、安積塾や昌兵黌からも生徒が集まり評判を呼んだ。経学とは、孔子の教えを研究する学問のことである。
ところが12月末の深夜、神田一帯を襲った大火で塾はあっけなく燃え、ほんの2ヶ月で元の木阿弥となってしまった。が、意外と八郎は飄々としたもので「これも天命」とあきらめも早かった。
ほどなく、清川に帰った八郎は、安政2年(1855年)、母・亀代を連れてお伊勢参りに向かう。この時、八郎が記した旅日記が
『西遊草』である。母のためにと、八郎は細かに旅の模様を記している。
同じ年、八郎と同行し清川に来ていた江戸の同志・安積五郎とともに湯田川温泉に遊びに行ったとき、お蓮という遊郭の酌婦に出会い、八郎は心引かれてしまう。妻・
お蓮との出会いだった。
安積が酔った勢いで、「節分の豆まきだ!」と、酒宴の場にお金をばらまいた。酌をしていた女たちは一斉にお金に飛びついたが、1人だけ哀しげな目をして座っていた少女がお蓮だった。清川で著述に専念していた八郎であったが、お蓮のことが忘れられず、結婚することを決意する。遊女・酌婦と言えば最も身分の低い女とされていたため、親の大反対をうけながらも二人は結婚し、仙台で新婚生活を送る。
安政4年(1857年)、八郎は、駿河台淡路坂に2度目の塾を開く。
この年、八郎は、千葉道場で山岡鉄太郎(鉄舟)と出会い、山岡の義兄・高橋泥舟とともに親交を深めるようになる。山岡は幕臣でありながら尊皇攘夷論派で、八郎とは良き同朋、理解者として親交が深まっていく。
徐々に門弟も集まり、順調に見えた清河塾だったが、またしても、火事で燃えてしまう。 |
 |
八郎は3回、江戸に塾を開いている。
安政6年(1859年)、神田お玉が池に3度目の塾を開き、「経学・文章・書・剣指南 清河八郎」という看板をかかげた。江戸広しといえど、学問と剣術を動じに教えられる学者は清河八郎意外、一人もいなかった。
「近頃、有名な学者がおいおい亡くなり、もはや恐れるような学者がいなくなってきました。あと3年も必死に学問すれば、私は大学者になれるでしょう」
このような内容の手紙を八郎は故郷に送っている。学者としての自信が伝わってくる内容だ。しかし、当時の日本を取り巻く国際的な政治状況が、八郎の学者としての成功をゆるさなかった。時代はめまぐるしく回転していたのだった。

